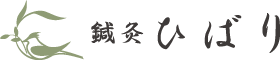がんと鍼灸

がんと鍼灸
鍼灸で施術をしていると、がんの方を対象とする場合があります。現代医学的にはがんを取り除き、再発しないようにしていきますが、鍼灸の場合は、血流をよくして免疫機能を上げることで、がんへの対処、体調をよくするための施術をすることになります。
免疫があがる、血流が上がることで、がん細胞が拡散したり、悪化をしたりするかもと考えることもあるでしょうが、転移する先の免疫機能がよくなれば、転移しにくくなるのではないかというので施術をすることになります。ただ、体表にがん細胞が生じてしまう場合がありますが、がん細胞そのものには刺激をしてはいけないので、がん細胞が集まっているところに直接、鍼をすることは禁忌になります。
このがんの転移に関して、提案された内容としては「バトソン静脈叢」という椎体の周囲・脊柱管内に存在する静脈ネットワークは弁構造がないためにうっ滞してしまいやすく、がん細胞なども停滞しやすいために転移するのではないかという話があります。報告例としては多くないですが、この「バトソン静脈叢」を介した感染についての論文があります。
「直腸潰瘍感染から骨盤・Batson静脈叢を介したB型連鎖球菌による椎体周囲感染と髄膜炎の1例」2011年
「バトソン静脈叢を介して胸膜転移を来した腎細胞癌の1例」1998年
「バトソン静脈叢」は血行性の悪性腫瘍の骨転移とも関係しているという話もあります。例えば、水の流れが悪い池があって、そこが汚染されれば、その池に関連するところは汚染されていってしまうという状況と考えてもいいのかもしれないですね。
がんを簡潔に考えていくとしたら、がんは身体にいらない物なのでゴミとして考えていくと、ゴミは片づけないと増えてしまいますし、腐ったものであれば周囲にも悪影響になってしまいます。人間の身体の中には、免疫・血流というゴミを片付けるシステムが備わっているので、免疫・血流をよくするということはゴミに対応する力にもなるので、がんにも対抗する力になるとも言えます。
単純に血流がよくなれば、がんが広がるという考え方をしてしまえば、がんは悪化してしまうことになりますが、免疫を上げるという部分もあれば、広がるのではなく、ゴミの処理をしていっていると言えます。
基本的に、鍼灸ではがん細胞を直接さして刺激をしない限りは、がんを悪化させることはないと言えるでしょうね。がん細胞を刺して悪化をしてしまう事例として出されるのは、メラノーマです。メラノーマは、ほくろと見分けがしにくいですが、皮膚科で見てもらえば診断することが可能です。
メラノーマは皮膚がんの一種で、悪性黒色腫と呼ばれていきます。鍼灸だと、「ほくろに鍼をするのはよくない」と言われますが、これはメラノーマの可能性を、我々は簡単に診断することができないので、注意をするために、言われていることです。ですから、ほくろには直接、鍼はしていくのはよくないです。
大きなほくろは移動することがないですが、小さいほくろは減ることもあるので、ほくろ付近は血流をよくする方がいいのではないかという考え方もできます。ということで、ほくろを瘀血の一種として捉えていけば、その場所には血流低下(血瘀)により瘀血が生じている場所と言えるので、ほくろ付近は治療対象と考えていくこともできます。
人によって違いもありますが、ほくろのある位置をみていくと、経絡走行に多い場合もあります。
西洋医学と東洋医学を合わせる
がんに対して西洋医学的治療に鍼灸を混ぜるのは、鍼灸師側からしてみたらいいものだと考えていくことが多いですが、西洋医学側からすると単純にいいこととは言いにくいので、がん治療に鍼灸を合わせるかどうかは、医師の考え方にもよります。医師自体が東洋医学に好意的であれば、東洋医学を取り入れることに積極的になることもありますが、医師の立場もあるので、微妙になることもあります。
どういうことかというと、東洋医学を取り入れていない病院内では、西洋医学的な治療を土台として治療をしているので、不確定要素(わからない、予測がつなない)には否定的になります。これは西洋医学の医師としての立場からしたら当然ですよね。西洋医学的にしっかりと管理しているので、違うことを入れてしまうと、予測不可能な自体になってしまい、その結果の責任を医師・病院のせいにされてしまっては問題になるので、医師側からしたら、外部からの施術を積極的に支援することは少ないです。
そのため、鍼灸で治療をしていくときに、「主治医」への相談はほぼしないことが多いです。もちろん、症状、治療経過によっても違いますし、患者さん側が、自分で医師に確認する場合もあります。それによって、鍼灸はやめて欲しいと言われる場合もありますし、肩の痛みや、腰の痛みに対してはいいのではという話が出ることもあります。鍼灸師側としては、肩の痛み・腰の痛みをやりながら、全体からの施術を加えることで、がん、がんに関連する症状にも対応していきたいというところなので、患者さんや主治医にどこまで誰に正確に話をするかは、非常に難しいところと言えます。
基本的には、入院時は病院の管理下で、病院に責任が生じるので、病院内での治療以外(鍼灸を取り入れているならばOK)はダメになることが多いですが、退院した場合は、個人の責任になるので、継続的な通院をしつつ、鍼灸などの代替医療を利用している人はいます。
がん患者に対する刺激量
がん患者さんは、身体が非常に弱っていることも多いですが、意外に体力もある方もいるので、治療に関する刺激に関しては、これでいいという決定をするのは難しい傾向があります。
さらに鍼灸は、切皮、刺入、響きのコントロールという刺激の要素があり、鍼灸の経験が少なく上手でなければ、コントロールしきれないので、切皮・刺入・響きの刺激が非常に大きくなってしまうことがあります。逆に、技術水準が向上すると、切皮・刺入・響きがコントロールされているので、刺激に気づかないうちに施術が進むことがあります。
単純な技術だけではなく、施術時間も重要になるので、上手になれば施術時間も非常にコンパクトにまとまっていくために、切皮・刺入・響きという刺激コントロール、時間という量も制御されているので、刺激量の決定は難しい問題の一つです。
そういった点で、経験が浅い方は、切皮・刺入・響きというコントロールが難しいのと、手際という量をコントロールすることが難しいので、よくある学校で習う全身治療をとりあえずやってみるという程度の施術だと、30~40分程度かかってしまうこともあるので、それで十分にもなることが多いです。逆に健康な人な人に取ってみたら、変化がでないことも多いです。その場合は、局所に対する施術を足すことで変化を出すことが可能になります。
ある程度、鍼灸治療に慣れている方であれば、全身への施術は20分程度で完結していて、後は置鍼時間や道具など様々な要素を加えていくことが多いので、初心者が行う時間の30~40分にまとまっていくことにもなります。
刺激に対する感受性は最終的には個人の体質にもよるので、まずは軽く施術をしてみて、悪化をしないか確認をし、次に刺激を増やしたり、減らしたりしながら施術を変化させていくことが大切になっていきます。
経験が長い人の施術を見ると、経験が長くなればなるほど、一つ一つの技術のスピードがあがり、経験値によって診察、取穴、施術のスピードもあがるので、初心者の頃は経験が長い人の施術をみると、すごく早く感じる、またはすごいのんびり感じるけど時間はかかっていないというのを体験できるのではないでしょうか。
がんと東洋医学
東洋医学は昔から使われていますが、今の医学用語として合わせている訳ではないので、これが「〇〇がん」だと断定するのは難しいですね。
ただ、その中でも「反胃(はんい)」という病能があり、食物が胃に停滞し貞貞、食べたものを吐いてしまうというものがあり、がんとして考えていくこともできます。古典にも病名は多くみられていて、詳細に調べている方もいます。
こうやって見てみると、昔から胃腸の問題というのがあったのですね。
実際に胃癌の方では、こういった胃腸障害としては吐いてしまうことがありますし、胃癌の方にお会いして診察をすると、「胃脘部」(上脘・中脘・下脘)に付近に硬結、冷えを強く感じることも多いです。施術をしていて、身体の反応がなく、なかなか変化しない人がいてなぜか変化をしないので、なぜかと考えていて、よく話を聞いたら、「過去に胃癌をしたが切除もしたし、その後の検査もして治った」から話してなかったということもありました。実際に腹診をしてみたら、お腹の硬結・冷えがあったので、お腹の硬結・冷えに対処するようにしたら、身体が変化しやすくなり、それから症状が軽減したこともあるので、現代医学には「治った」としても、東洋医学的には「治っていない」ということがあるのかなと考えるきっかけになりました。
胃癌の人でも、この胃脘部に硬さがある人もいれば、なかった人もいるので、その違いが何かという検証は多くの人をみてみないと分からないので、いまのところ、違いは分からないです。東洋医学では感覚で診察をしていきますが、硬さがあって分かれば診断できますが、硬さがないと診断できないので、こういう場合は、やはり、画像や検査所見は確定できるので客観的な評価は重要になりますね。
がん患者さんでも、年を取ってくれば、膝が痛みが出たり、腰が痛くなったりすることがありますし、膝や腰に対して施術をしていったら、胃の調子もよくなるということは、鍼灸の施術ではよくあることになります。なぜかといえば、膝には脾・胃の経絡が関係することが多く、この局所だけの施術をしたとしても、この2経絡のアプローチをしていることになるので、結果的に脾胃(胃腸)の調子があがることも多いです。
腰部への施術でも腰は生命の根本の腎に対処することにもなりますし、三焦兪までいけば三焦は気と津液の通路になるので、全身の循環改善にも役立つことになります。このようにがんとは関係ないと考えられる局所対する施術をしたとしても、東洋医学は気血や経絡でつながっているので、全身への大きな変化が生じることがあります。
がん自体は、はるか昔から存在しているものなので「瘤(りゅう)」という言葉で呼ばれている、「腫れ」「固まる(硬い」病気と言えます。有名な言葉としては乳がんとして考えらえるものが「乳岩(にゅうがん)」という言葉もあります。歴代の文献では、停滞(気滞、痰湿、瘀血など)によって生じたり、外邪、気血の不足によって生じたりすることもあると考えているので、原因は非常に様々になっています。
がんはもともと細胞分裂する際のエラーで発生し、若い頃は免疫の力も強く、退治されていきますが、加齢とともに、細胞分裂のエラーも増え、免疫が低下してしまうと、がんが増えると考えていくことができます。そのため、がんは高齢化によって増えやすい傾向があります。
中医学では、加齢をしていくということは、身体の持っている力(気・血・津液・精・陰・陽)が低下してしまったり、流れが悪くなって滞り(気滞、血瘀、痰湿など)が発生してしまったりすることで身体の状態が悪くなってしまいます。この結果として現れてくるのが病気であり、「がん」にもなるので、中医学では身体の状態を確認して、気血津液などの状態をしっかりと見定めていく必要があります。
身体の持っている力の低下では、生命力の根本となるのが精であり、精の不足は陰気・陽気の不足にもつながりやすく、加齢になると体内に水分量が低下していってしまうために、加齢は陰液不足であるという考え方をすることもできます。陰液が不足をしていくと、乾くだけではなく、熱のコントロールをすることができないので、のぼせも生じやすい状態になります。陰液不足で発生した熱は内熱となり、内では気血の消耗を進ませてしまう結果、腫瘍を形成してしまうという考えもあります。
陰液不足だけではなく、気の不足が強くなり、陽気不足となってしまった場合も、気の推動作用が低下してしまい、気血の流れが悪くなり、内寒の凝滞性・収引性により、気血の停滞を強く発生させ、腫瘍を形成してしまうと考えていくことができるので、中医学では人の身体は気血の流れをよくしていくことが非常に大切になっていきます。