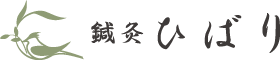むずむず脚症候群(RLS:レストレスレッグス症候群)と東洋医学

むずむず脚症候群とは
むずむず脚症候群は、動いているときには何も感じないので、休もうとする(座ったり、横になったり、寝たり)と、足にむずむず、虫がはうような、休んでいられないような不快な感覚が生じてしまうものになります。この不快な感覚は動いているときには感じないので、不快な感覚が生じたら、足を動かしたり、歩いたりしないと落ち着かない状態になります。
動かないで休もうとしているのに休めないので、休憩(レスト)が無い(レス)、足(レッグス)を合わせて、レストレスレッグス症候群と呼ばれています。
身体の感覚は人それぞれなので、痛み、ほてり、虫、ゆれなどにように表現は変わりますが、ゆっくりと休めない状態が継続するので、非常にストレスにもなり、精神的にも肉体的にも辛い状態が続いてしまいます。
病気は発生原因から考えると、一次性と呼ばれる原因がはっきりと分からないものと、二次性と呼ばれる病気が原因によって生じる場合があります。二次性の場合は、慢性腎不全や貧血、糖尿病、パーキンソン病などの疾患があり、病気が問題になるだけではなく、神経や筋肉の働きにも影響が発生している場合があります。
原因が分からない場合は、治療方法があるわけではないので、症状が落ち着くまで待つという状態にもなってしまうことがあります。子どもに生じる場合もありますが、多くは40歳以上で、比較的、女性に多いと言われています。
東洋医学的な弁証の出し方
東洋医学は身体の状態が変化してしまうことで、何かしらの状態(症状)になってしまうと考えていくので、「むずむず脚症候群」だからというのでは、東洋医学的な身体の状態としては確定できない傾向があります。
東洋医学的に身体の状態を把握する場合は、臓腑、気血津液などについて考えていく必要があります。
体表面を、はう、むずむずというような異常な感覚が足に動きまわるということは、いくつかの原因を考えていくことができます。まずは体表面を覆っている衛気が弱くなってしまったために、外邪が入りやすい状態になっているというもので、加齢によって生じているのであれば、この衛気の虚(つまり気虚)の状態も考えていくことができます。ただ、気虚の状態であれば、衛気による腠理のコントロールができなくなってしまっている状態にもなるので、自汗や悪風、倦怠感が発生しやすい傾向があります。気虚の場合は夜間に症状が強く生じるという特徴ではなく、疲労によって気不足が強くなると生じやすくなるので、むずむず脚症候群が生じる日と生じない日という変化がある可能性があります。
気虚が原因として発生しているのであれば、気虚を生じやすい心、脾、肺、腎が原因の可能性もあるので、気虚だと考えたのであれば、今度は臓腑を確定していく必要があります。
体表面がむずむずするという感覚があるということは、風邪(ふうじゃ)が身体で暴れているという可能性も考えていく必要があります。この場合は、単純に外邪の風邪(ふうじゃ)が身体で暴れているという状態として考えるのではなく、内風のことも考えていく必要があり、内風は血虚、陰虚、熱によって発生することが多いので、どの状態から発生しているのかを確認する必要があります。
血虚が生じているようであれば、心血虚・肝血虚のどちらの状態が発生しているのか考えていく必要がありますが、心・肝ともに血虚となっている心肝血虚の場合もあります。心血虚になっているのであれば、心脾両虚(気血両虚)になっていく可能性もあります。
血虚が進行していくと陰虚にもなります。陰虚は身体の陰液の不足と関係していますが、陰虚の代表的な症状は夜に悪化しやすいです。さらに身体の陰液不足は東洋医学的に加齢が発生していると言えるので、40代以上から発生している状態で、夜に寝るときに「むずむず」するのであれば、陰虚による内風も関係しやすい状態になります。
陰虚が生じやすいのは、肝、心、肺、腎であり、脾もありますが、学校教育上では出てこないので、脾以外の4臓で考えていくことになります。
肝陰虚が進行すると肝陽亢進となり、肝陽化風というふるえやひきつりが生じやすい状態でもあるので、むずむず脚症候群は陰虚傾向が該当しやすい傾向があります。
他にも、腎精不足により滋養できない場合でも生じていくので、まずは加齢により発生しているのであれば、何が(気血津液)問題で、どうなっているのか(虚実)を考え、どこ(臓腑)を出していくことになります。
その他の状態としては、痰湿、気滞、血瘀は気血の流れが悪くなることで、正常な身体の活動ができていない場合もあるので、虚だけではなく、実の病能も確認していくことが必要になっていきます。
弁証は一つに断定できる場合もありますが、虚も実もあるという、虚実挟雑(きょじつきょうざつ)もあるので、まずは、どのような状態なのかをまとめてみて、それから最初は何で治療するのか考え、結果をみつつ、次をどうするのか考えていくことになります。
配穴は気血津液に合わせた配穴、臓腑の状態に合わせた配穴をしながら、後は症状が生じている場所をどう処置していくのかというのが大切ですが、全体の調節だけで様子をみて、局所を足していくのが慣れていないときにはやりやすい治療ですね。局所の処置を考えていくには、経絡の走行を意識しながら行うことも足していくのがよいですね。